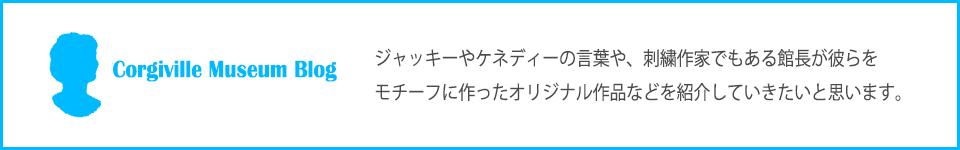ジャッキーと恋に落ちた時代
corgiville (2013年1月24日 01:12)
ジャッキーに惹かれる人間の思いを代弁してくれるような文章だと感じたのは、「NEWS WEEK 日本版」1994年6月1号の彼女の追悼特集に寄稿されたSarah Crichtonのコラムでした。
タイトルは「さようならアイドル」。全文に同感なのだが、一部を抜粋してみたいと思います。
♪今の時代におとぎ話が存在する余地はない。その上、現代の女性に期待されるものはあまりに 多く、すべての女性たちの夢を体現するような人物はもう望めないかもしれない。
だが、私たちがジャッキーと恋に落ちた時代は、今よりもずっとシンプルだった。私たちがお姫様になる日を夢見ていたころ、彼女はまさにお姫様だった。大人になった私たちが自立をめざしていたとき、ジャッキーはすでに自立していた。
彼女はいつも、一歩先をいっていた。良き母あるいは良き妻であること、いつも美しくあること常に「関心を集め続ける」こと──私たち普通の女が格闘しているあらゆることを、ジャッキーはやすやすとこなしているように思えた。
涼やかな鎖骨と、エレガントで美しい腕をしていたジャッキー。彼女はその腕で赤ん坊をあやし、男たちとダンスを踊り、大きな動物を手なずけた。たいていの女は自分の肌に不満だったが、ジャッキーの肌は内側から輝いていた。
.........
♪芸能カメラマンが群がろうと、彼女はその間を平然とかきわけて歩いた。ニューヨークっ子にどんな陰口をたたかれても、生き生きした「面白い人生」を追い求め続けた。
.........
♪働いて正当な報酬を得るのに謝ったりしなかったし、過去を弁解することもなかった。交際相手が既婚の男性でも、平然と腕を組んで出かけた。気がむけばカメラマンにほほ笑みさえした。
.........

私がジャッキーを尊敬する点は「過去を弁解することもしなかった」というところです。
世界中の非難を浴びたオナシスとの再婚や破綻をみせたその結婚生活、そしてオナシスの遺産をめぐっての義理の娘クリスティーナとの争い。
ジャッキーほどの人物なら、後に自叙伝でも出版して、いくらでも自分の都合いいような話だって書けたはずです。自伝出版の誘いだってかなりあったでしょう。
でも、結局、亡くなるまで彼女は自分のことを自ら語ることはしませんでした。
たいして大物でもない芸能人や、スポーツ選手の親が周囲に勧められたとはいえ、すぐに手記を出版したりする安っぽさとは、比べ物になりません。